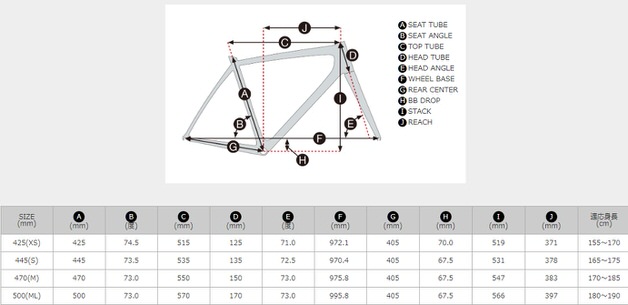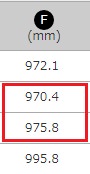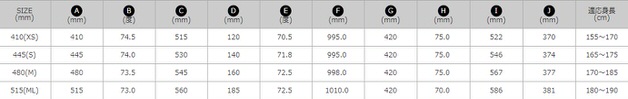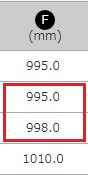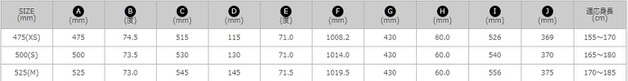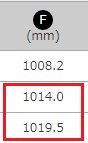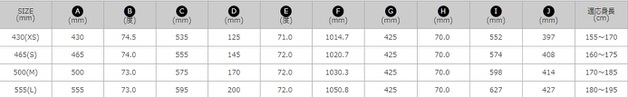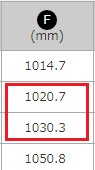自転車を買おうと、いろいろ調べてみると・・
「ホイールベースが長いと良いよ!」みたいな情報にぶち当たった!
・・ホイールベースって、何?
ホイールベースはロードバイクなどの自転車における、超重要パラメーターです。
これが長い・短いによって、乗り心地といった特性がまったく変わってきますし・・
フレームを交換しない限り変えられないので、そういった視点からみても大事です。
しかしもしあなたが、ロードバイクなどの自転車を買ったばかり!
もしくは、これから買おうかな?と検討している・・
そういった状況なら「ホイールベースって何?」と思うのは、自然なことだと思います。
なのでこの記事では、自転車のホイールベースって何?
どのくらいから長いと言えるの?長い・短いと自転車はどうなるの?
といったところを徹底解説していきます。
目次
ホイールベースは「前輪と後輪の距離」
まず、結論からですが・・
ホイールベースとは「前輪と後輪の距離」のことです。
具体的には「前輪の軸」と「後輪の軸」のあいだの距離ということですね。
自転車の外観は、

こんな感じで・・
まず「前輪の軸」の位置は、

この、矢印で指すところです。
そして「後輪の軸」のほうは、

ここですね。
なのでこれらの間の距離、つまりホイールベースは・・

この、水色の線で示す長さとなります。
見方を変えると「ふたつのタイヤの接地点同士の距離」とも言えて・・

こんな感じで、地面に設置している2点同士の距離ともできます。
(前輪の軸・後輪の軸の間の長さと、まったく同じになるはずです)
メジャーなどで計測するときは、こっちの方がやりやすいでしょう。
自転車のホイールベースとは何?の答えは、以上となります。
長いと「安定性」がアップする

じゃあホイールベースが長い・短いと、自転車はどう変わるの?
まず、ホイールベースが「長い」ほうからですが・・
ホイールベースが長いと、自転車は「安定性」に優れた乗り心地になります。
つまり、
- 腕の力を抜いてもハンドルがふらつかない
- カクッとしたコーナリングにならず、安定して曲がれる
- 衝撃を受けても自転車がブレにくい
こんな感じの特性を得られる、ということです。
ホイールベースとは、ふたつの接地点の距離なので・・
その長さは人間でいう「足幅」に相当します。
左足と右足、ふたつの接地点に相当するということですね。
そして安定したいとき、足幅を広げるか?狭めるか?
そう聞かれたらおそらく「広げる」と答えるのではと思います。
体重を支える面を広くすることで、どっしり支えますよね。
そのほうが押されたりしても、しっかり立っていられると思います。
実際に力士、ウェイトリフティング、ラグビーのぶつかり合うポジションといった人たちは・・
足幅を広げて構えることで、体をしっかり安定させています。
そのほうが安定するので、みんなそうしているということでしょう。
自転車も同じなので、ホイールベースは長いほうが・・
車体がしっかり支えられ、安定することになります。
なので例えば、
- ふらつきに体力を削られず、長距離を走りたい
- サイクリングロードのような走りやすい道を、ひたすら直進する機会が多い
- 素早くシャキシャキした乗り味には興味が無い
ホイールベースが長い自転車は、こういったニーズを持つ人に向く!と言えます。
実際に、長距離を安定して走るための「エンデュランスロード」といった自転車は・・
ホイールベースを長くなっていて、それによる安定性アップを狙っていることが分かります。
なので安定性が欲しいなら、そういったところから自転車を選ぶと後悔しにくいでしょう。
短いと「機敏さ」がアップする

逆にホイールベースが「短い」とどうなる?
ホイールベースが短いと、自転車は「機敏さ」が高い乗り味になります。
具体的には、
- ちょっと体を傾けただけで、自転車がスパッと舵を切る
- 足に力を込めると、すばやく反応して加速する
- 地面の感触を、ダイレクトに感じ取りやすい
こういった特性が目立つようになってきます。
ホイールベースが短いということは、人間で言うと「足幅が狭い」ということです。
ボクシング、テニス、サッカーなど・・
機敏な動きが必要なスポーツではみんな、足幅を狭くして素早いフットワークを実現しています。
自転車も同じように、ホイール同士の幅が狭いほうが・・
すばやく反応する、機敏な自転車を実現できるということですね。
なのでホイールベースが短い自転車は、
- レースで競うため、瞬発的な加速やコーナリングがしたい
- 混雑した街中を、機敏な動きでひらひらと走り回りたい
- どっしりした安定感は求めない
こういったニーズには、しっかり応えてくれるでしょう。
実際「レース向けロードバイク」といったカテゴリに入る自転車は・・
ほとんどの場合で、ホイールベースがギリギリまで短く設計されています。
それによって、レースに必要となる機敏さを得ているのでしょう。
長い・短いの基準は、何mm?
ホイールベースが長い・短いの効果は、そんな感じなのですが・・
じゃあ具体的に「何mm」を基準に、長い・短いと言えるの?
結論から言うと、ホイールベースの基準は「1,000mm」!
これより長いとホイールベースは長い、これより短いとホイールベースは短い!
というのが、この記事なりの結論になりました。
そして自転車のホイールベースは、メーカーの公式ホームページなどで簡単に確認できます。
もしわかりにくければ「ジオメトリー」などの項目を探すと、おそらくあると思います。
なのでこの長さを軸に確認すれば、自分の自転車のホイールベースは長いのか?短いのか?が分かることになります。
じゃあホイールベースの基準を「1,000mm」と言い切った根拠は、何?
以下、解説していきます。
「レース系ロードバイク」だと、970mm程度
自転車には、いろいろな種類がありますが・・
中でもホイールベースが「短い」自転車の代表は、「レース系ロードバイク」です。
レースに出るようなロードバイクには、ライバルを抜き去るための瞬間的な加速とか・・
自分の位置をすばやく変えるための、キレのいいハンドル操作といったものが必要になります。
なのでそれらを実現するため、ホイールベースは短く作られることがほとんどです。
なのでレース系ロードバイクのホイールベースは、何mm?
ここを実車ベースで確認することで・・
ホイールベースが「短い」自転車の基準が、分かってくるわけですね。
それでは、レース系ロードバイクの実例を見ていきましょう。
車種は、超有名ロードバイクメーカー「GIANT」の「TCR」シリーズを参照してみます。
フレームサイズは多くの人が選ぶであろう、「S」と「M」を見てみます。
GIANT公式ホームページ TCR SL ジオメトリー表より引用
実際に見てみると、こんな感じで・・
ホイールベースの長さは「970mm」程度となっています。
他のメーカーのレース系ロードバイクを見てみても、ホイールベースはそんなものでした。
なのでこの長さが、ホイールベースが「短い」自転車の基準!と言えます。
「エンデュランス系ロードバイク」だと、1,000mm程度
次に「エンデュランス系ロードバイク」を見てみます。
エンデュランス系ロードバイクとは、レースで勝つというよりは、長距離を疲れずに走るといったことを目指す自転車で・・
レース系と比べると安定性とか、衝撃の吸収性といったものを重視します。
そしてそれを実現するため、ホイールベースは「長め」に設定されるものです。
じゃあエンデュランス系ロードバイクの、具体的なホイールベースの長さは?
ここでは同じく「GIANT」の「DEFY」シリーズを参照します。
TCRがレース系の代表、DEFYがエンデュランス系の代表・・みたいな扱いの自転車ですね。
GIANT公式ホームページ DEFY ADVANCED ジオメトリー表より引用
実際に見てみると、こんな感じで・・
DEFYのホイールベースは「1,000mm」程度と言えるでしょう。
1,000mmよりやや短くはありますが、誤差の範囲と言えそうです。
他社のエンデュランス系ロードバイクでも、長さはそんな感じです。
なのでこれがホイールベース「長め」の自転車の、基準と言えます。
「クロスバイク系」だと、1,020mm程度
最後に「クロスバイク系」の自転車を見てみます。
クロスバイクはロードバイクと違って、レースではなく「街乗り」といったものを想定しますので・・
エンデュランス系ロードバイクと比べてもさらに、安定性や乗り心地が優先されるものです。
なのでそれを実現するため、「長い」ホイールベースになってきます。
じゃあクロスバイク系自転車の、具体的なホイールベースは?
GIANT公式ホームページ TCX SLR ジオメトリー表より引用
GIANT公式ホームページ Escape RX ジオメトリー表より引用
ふたつの車種を参照してみましたが、こんな感じです。
ざっくりまとめるなら、ホイールベースは「1,020mm」程度だと言えるでしょう。
他社のクロスバイク系自転車もいろいろ見てみましたが・・やっぱり、ホイールベースはそんな感じでした。
なのでこれが、ホイールベースが「長い」基準の自転車になってきます。
長い・短いの基準は「1,000mm」
ここまでをまとめると、ホイールベースは・・
- 短い:970mm程度
- 長め:1,000mm程度
- 長い:1,020mm程度
こういうことになります。
これらの情報を、すごくざっくりと束ねると・・
ホイールベースの基準は「1,000mm」!
これより短ければ「短い」自転車で、これより長ければ「長い」自転車!
そう言って、大きな間違いではないと思います。
とはいえ、基準はフレームサイズによっても変わってくるので・・
あくまでも一般的なフレームサイズ選択における、一般的な基準ということですね。
長い・短いと言っても、ほんの数cmしか違わないのでは?と思われるかもしれません。
しかし自転車パーツというものは、数cmどころか数mmの違いでも、乗り味に違いが出てくるものです。
サドルの高さとかハンドルの遠さとかが、代表的なところですね。
そして上で挙げた「短い」自転車と「長い」自転車とでは、ホイールベースは5cmもの差が出てきますので・・
この要素だけでも、まったく別の自転車!とはっきり分かるほどの乗り味の差が生まれるでしょう。
生活の中で使うなら、ホイールベースは「長い」ほうが有利
最後に、個人的な考え方をかなり含みますが・・
生活の中で使う自転車なら、ホイールベースは「長い」ほうが有利
この考え方を解説してみます。
ホイールベースは長いほうが、安定性に優れる!
短いほうが、機敏さに優れる!
というのは、上で解説した通りです。
そしてもし買った自転車を、生活の中で使い倒すのであれば・・
つまり、
- 自転車通勤
- 街中を走り回る
- ちょっとした自転車旅
こういった用途を中心に使っていくのであれば・・
ホイールベースは「長い」自転車にしておくほうが得!と考えます。
なぜ、そう思うの?
生活の中で便利に使うのが中心なら・・
レースレベルの機敏さが求められることはとても少ないからです。
ホイールベースが短いと、小回りや加速性能が高くなるわけですが・・
そこで追求されるのは「レースで勝つ」ための、ハイレベルなものだったりします。
なのでホイールベースが「長い」自転車であっても、普通に乗るための小回り・加速性能は十分にあります。
そして「安定性」は、とにかく少しでも上げたい要素になってきます。
安定性は高ければ高いほど、ふらつきにくく疲れにくくなりますので・・
こっちを優先して上げておくほうが、ほとんどの状況において有利なわけですね。
参考までに現在、私自身が持っている自転車は、
- サーリークロスチェック:1,014mm
- ブロンプトン:1,045mm
このようにいずれも、ホイールベースが「長い」と言えるものを選んであります。
そしてそれぞれの安定した乗り味に、とても満足しています。
もちろん、好みやニーズは人それぞれです。
そして・・とにかくキビキビと、切れ味のいい動きをする自転車が欲しい!
そう思われるのなら、ホイールベースは「短い」ほうが合うことになります。
しかしもしレースなどを優先せず、街乗りといった一般的なライドに使うなら・・
ホイールベースは「長い」自転車を選ぶほうが、後悔が無いのではと思います。
ホイールベースは自転車の、ちょっとマニアックな見どころですが・・
乗り心地への影響はとても大きく、しかもパーツ交換などで後から変えられないパラメーターです。
なので自転車を選ぶときは、じっくり考えておくほうがいい要素だと思います。
今回は自転車のホイールベースについて、知っていることを書いてみました。